「終末期~危篤、死のとらえ方」についてのスキルアップテストです。
そもそも終末期とは?
終末期とは、現代の医療技術でも回復の見込みがなく、数週間から数ヶ月のうちに死が訪れると予想されてから、亡くなるまでの期間のことを言い、「ターミナル期」とも言います。
終末期の介護については
【終末期の介護】
(ターミナルケア)~死を目の前に無神経にならないために~
をご参考ください。
まずは出題基準から見ていきましょう。
出題基準をみることで、どんなことが問われるかを把握できます。
大項目:死にゆく人のこころとからだのしくみ
中項目
- 「死」の捉え方
- 終末期から危篤、死亡時のからだの理解
- 「死」に対するこころの理解
- 医療職との連携
小項目
- 生物学的な死
- 法律的な死
- 臨床的な死
- 身体の機能の低下の特徴
- 死後の身体的変化
- 死に対する恐怖・不安
- 「死」を受容する段階
- 家族の「死」を受容する段階
- 呼吸困難時に行なわれる医療の実際と介護の連携
- 疼痛緩和のために行なわれる医療の実際と介護の連携
「・・・」にはいる言葉を答えてください。
最初はわからなくて当然です。
「?」のまま読み流しても大丈夫ですよ。
記事の最後には答えられますから。

スキルアップテストに挑戦
1. 生物学的な死とは生体のすべての「・・・・」が停止し、生命が不可逆的に失われた状態をいう。
2. 「・・・」な死とは、心臓・肺・脳の3臓器の機能が不可逆的に停止した状態をいう。
3. 回復の見込みのない終末期にある人が、延命のためだけの医療を拒み、人としての尊厳を保ちながら自然な死を迎えることを「・・・」という。
4. 現代の医療技術でも回復の見込みがなく、死期が近づいた状態にある人に対して行われるケアを「・・・・・・・」という。
5. バイタルサインとは、生命徴候と言われ、一般に脈拍、呼吸、「・・」、体温の4つの指標からなる。
6. キューブラー・ロスの死にゆく人々がたどる心理過程において、健康な人への羨望や嫉妬の感情が起こる段階を「・・」の段階という。
7. がんによる苦痛がある場合は、放射線治療や、「・・・・」が行われる。
解答

- 生理機能
- 臨床的
- 尊厳死
- ターミナルケア(エンドオブライフケア)
- 血圧
- 怒り
- 化学療法
解説
①生理機能
生理機能とは、生物体が生きるために起こるからだの現象や
呼吸、排泄、血液循環などの、生きていく為の身体の機能。
②不可逆的な死
不可逆とは、再び元に戻らないこと。
不可逆的な死とは、臓器の機能が不可逆的に停止した状態をいう。
医師は、心拍停止・呼吸停止・瞳孔散大の3大徴候を基に死亡確認を行う。
③尊厳死
尊厳死とは、回復の見込みのない終末期にある人が、延命のためだけの医療を拒み、人としての尊厳を保ちながら自然な死を迎えること。
生前に尊厳死を選択するリビングウィルがなされている場合、執行することが法的に認められていないため、強制力がない。
リビングウィル…生前の意思表示の事。
④ターミナルケア(エンドオブライフケア)
ターミナルケアとは、終末期にある人を対象として行われるケアのこと。
「人生の最期までその方らしく、充実した生活を送っていただく。
できる限り苦痛を和らげ、穏やかな気持ちで最期を迎えられる。」
ことが私たちがすべき支援のあり方だと思います。
在宅でのターミナルケアは、利用者が家族とともに安楽に過ごすことを目標とし、複雑な医療処置を行わないことを原則としています。
⑤バイタルサイン
バイタルサインとは、「生命兆候」とも言われ、体温、血圧、脈拍、呼吸など、人体の最も基本的な情報の事。
⑥キューブラー・ロスの死に行く人々の心理過程
エクストリーム介護福祉士国家試験対策サテライトセミナー
キューブラー・ロスは、死に行く人々の心理過程を5段階に分けて説明している。
死の受容までにはプロセスがあることを発見したが、すべての患者が同様のプロセスをたどるわけではない。
- 第1段階…「否認」
- 第2段階…「怒り」
- 第3段階…「取引」
- 第4段階…「抑うつ」
- 第5段階…「受容」
⑦がんの化学療法
薬を使う治療の事。
抗がん剤、ホルモン剤、免疫賦活剤などを用いる。
痛みの緩和や、症状を和らげるために
鎮痛剤や、制吐剤などが使用される。
国立がん研究センターHPより抜粋
スキルアップテスト②
つぎの中から、間違っているものを1つ選んでください。
1. 「臓器の移植に関する法律」により、一定の条件を満たした場合に限り、脳死の状態の人から臓器移植が可能になった。
2. 終末期の身体的変化として、思うように身体を動かすことができなくなり、寝返りが打てず、長時間圧迫を受けた皮膚の血液循環が悪くなり、 褥瘡ができる。
3. 危篤状態の身体的変化として、鼻翼呼吸や、下顎呼吸などが見られる。
4. 死後の処置は、看護師や介護士などが、死後硬直の後に行う。
解答・解説

1. は設問のとおりなので、〇。
2. は設問のとおりなので、〇。
定期的に体位交換をする必要がある。
3. は設問のとおりなので、〇。
4. 死後の処置は、死後硬直の前に行う。
よって解答は、4
死後硬直
死後硬直とは、死体の筋肉が硬化する現象のこと。
20℃前後では通常、死後2~3時間程度経過してから始まり、死後12時間ほどで全身に及ぶ。
記事の最後に
記事の最後にもう一度、スキルアップテストに挑戦してみましょう。
スキルアップテスト①
1. 生物学的な死とは生体のすべての「・・・・」が停止し、生命が不可逆的に失われた状態をいう。
2. 「・・・」な死とは、心臓・肺・脳の3臓器の機能が不可逆的に停止した状態をいう。
3. 回復の見込みのない終末期にある人が、延命のためだけの医療を拒み、人としての尊厳を保ちながら自然な死を迎えることを「・・・」という。
4. 現代の医療技術でも回復の見込みがなく、死期が近づいた状態にある人に対して行われるケアを「・・・・・・・」という。
5. バイタルサインとは、生命徴候と言われ、一般に脈拍、呼吸、「・・」、体温の4つの指標からなる。
6. キューブラー・ロスの死にゆく人々がたどる心理過程において、健康な人への羨望や嫉妬の感情が起こる段階を「・・」の段階という。
7. がんによる苦痛がある場合は、放射線治療や、「・・・・」が行われる。
スキルアップテスト②
つぎの中から、正しいものを1つ選んでください。
1. 「臓器の移植に関する法律」により、一定の条件を満たした場合に限り、脳死の状態の人から臓器移植が可能になった。
2. 終末期の身体的変化として、思うように身体を動かすことができなくなり、寝返りが打てず、長時間圧迫を受けた皮膚の血液循環が悪くなり、 褥瘡ができる。
3. 危篤状態の身体的変化として、鼻翼呼吸や、下顎呼吸などが見られる。
4. 死後の処置は、看護師や介護士などが、死後硬直の後に行う。
解答は上に戻って、再度確認してください。
何度も繰り返すことで、覚えられます。
また、お看取り間近の利用者様がいらっしゃる場合の、心がまえのヒントにもなります。
「死」のとらえ方を理解し、こころとからだの状態を理解することで、その方にどう寄り添ったらいいのか?おのずと考えられるようになります。
本当の怖さや、悲しさは、ご本人や、家族にしかわかりません。
けれど、 自分に置き換えてとか、自分の家族だったら?
と想像してみてください。
きっと、恐怖や、悲しさに見舞われると思います。
「わからない」とか、なにも考えずに支えることなんかできません。
理解しようとすることが、寄り添うことのひとつだと
私は思います。
みなさん、お疲れ様でした。
介護福祉士 華珠, プロフィール

関連記事
「ああ、いい人生だった」と思ってもらいたい。
現場でも役に立つ内容になっていると思います。
ご参考にしていただければ幸いです。
介護福祉士国家試験 頻出テーマ動画
20分「~ながら」、聞き流しに最適
エクストリーム介護福祉士国家試験対策サテライトセミナー
1時間「~ながら」に聞き流しに最適
パワースポットで合格祈願!
ぜひ、パワーを受け取ってください。
「皆さんの合格心から願っております。」
スローな動画なので、勉強の合間にまったりしたい方にもおすすめです。
おすすめ記事
地域の目として、介護士として、どう行動したらよいか?
アツくなっています。
スポンサーサーチ
・【早い者勝ち!】 あなたのお名前、残ってる?
資料請求も簡単にできます。
人気記事
みなさんおつかれさまでした。
いつもお読みいただきありがとうございます。
介護福祉士 華珠, プロフィール
おすすめテキスト
法改正の部分は正直、独自に調べるのは難しい。
解りやすく、学びやすくしてくれています。
成美堂出版の回し者ではないのですが、本のタイトルで手に取るものが、たまたま成美堂出版の本で、うちには何冊もの成美堂さんがあります。
ずぼらの私には要点まとめとかかかれてしまうと、手に取ってしまいます(笑)
こちらのテキストは
確かに、出題頻度の高いキーワードをピックアップしていますので、
効率よく勉強ができると思います。
しかし、より頭に定着させるには、過去問題も一緒に解くことです。
問題集や、過去問、やるときに、びしっとまとまってます。
オールカラーで、まあ、大きいですけど、その分見やすいです。
参考書というか、図鑑みたいな感じですね。
わからないキーワードがあったときに、索引ですぐに調べられますし、わかりやすくまとめられていますので、とっても便利です。
1~2年前の中古でも全然いいと思います。
スポンサーAD
・【早い者勝ち!】 あなたのお名前、残ってる?



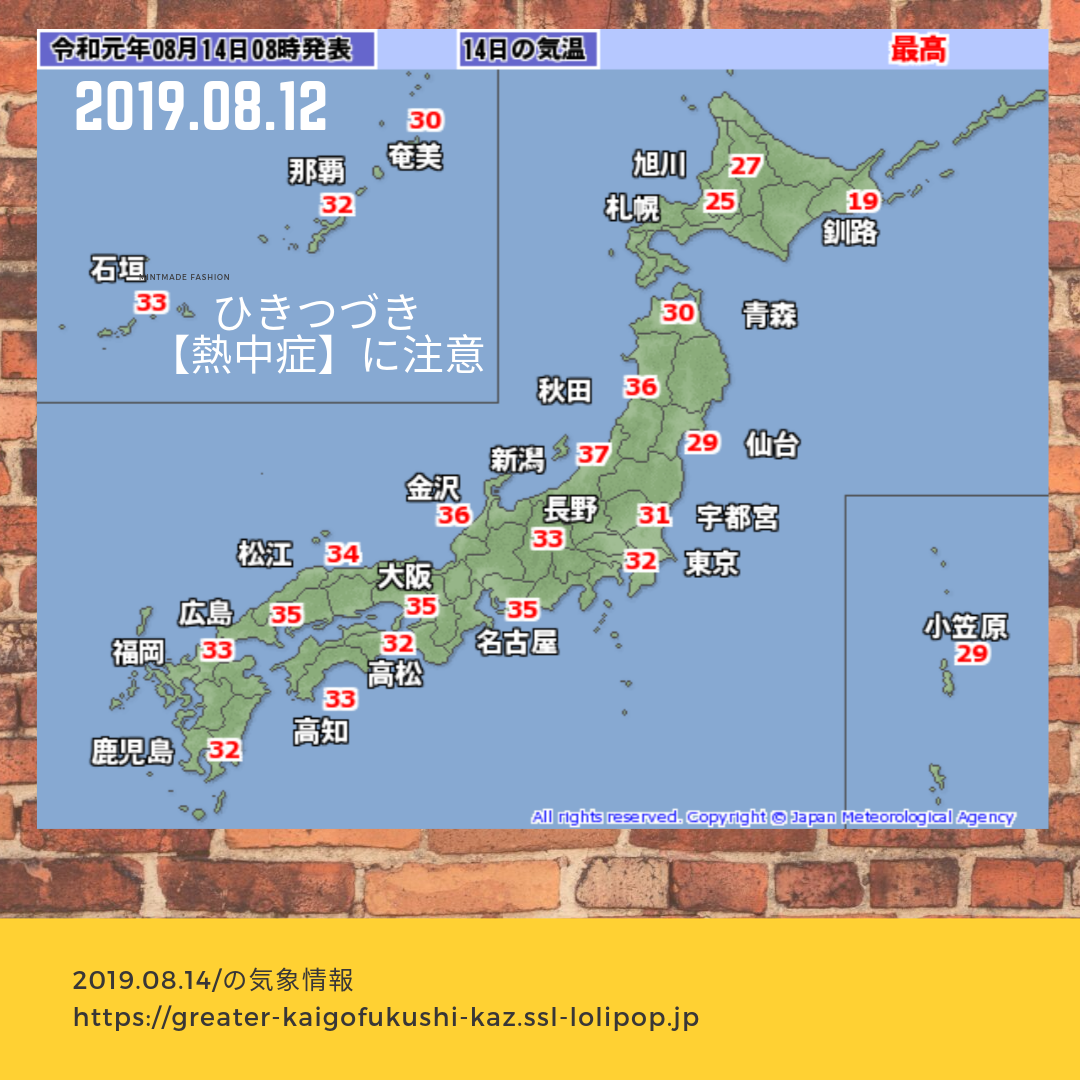
コメント