介護の経験があっても、改めて質問されると答えづらいところは、きちんと答えられるように整理しておきましょう。
目次
・ボディメカニクス
・ベッド上の姿勢
・過去問題
(第31回介護福祉士国家試験問題)
ボディメカニクス

ボディメカニクスとは、力学的原理を活用した介護技術の事。
介護者の負担が少なくなり、腰痛予防になります。
原則
- 支持基底面積を広くし、重心を低くする。
- てこの原理を使う
- 膝の屈伸や、水平移動を利用し、腕力に頼らない。
- 介護者は体をひねらない。
- 足先は移動方向に向ける。
- 利用者に接近、密着する。
- 手足をまとめる。
- 大きな筋群を使う。
支持基底面

「身体を支える為に、床と接している部分を結んだ範囲のこと」
支持基底面積を広くし、重心を低くするほど安定します。
身体の重心が、支持基底面から出てしまうと、バランスをとることが難しくなります。
ジョイリハさんのHPより
てこの原理

「持ち上げるものの重さが同じならば、支点から作用点までの距離が短いほど、必要な力は小さくて済む」
(絵でいうと、地球が作用点、石が支点、人が力点)
持ち上げようとするものが自分に近いほど、持ち上げる力は小さくて済みます 。
利用者に接近、密着する
肘や膝を支点にする。
に関わってきます。
介護者は体をひねらない。
身体をねじる状態は腰痛の原因になります。
手足をまとめる
対象の両手、両足を組む事で摩擦が少なくなり、移動しやすくなる。
(摩擦… 運動する物体が他の物体にふれることによって受ける抵抗 )
大きな筋群
大きな筋群(大筋群)とは、大胸筋、広背筋、腹直筋などのこと。
腕や足、指先だけの力で動作するより、大きな筋群を使用した方が力が大きく、介助時の負担が減る。
ベッド上での姿勢
- 仰臥位(ぎょうがい)
- 側臥位(そくがい)
- 端座位(たんざい)
- 起座位(きざい)
仰臥位(ぎょうがい)

側臥位(そくがい)

端座位(たんざい)

起座位(きざい)

看護rooさんのHPより引用
スポンサーads
Tポイントで始められる投資【SBIネオモバイル証券】過去問題 (介護福祉士国家試験第31回より)
(総合問題1)
次の事例を読んで、答えなさい。
[事 例]
Fさん(78歳・男性)は、妻(75歳)と二人で暮らしていた。
1か月前に脳出血(cerebral hemorrhage)で入院して、左半身の不全麻痺がある。
立ち上がりや歩行に介助が必要なため、杖や手すりを使用した歩行訓練をして、杖歩行が可能になった。
病院のソーシャルワーカーの勧めで、Fさんは介護保険の申請をして結果を待っていた。
ある日、「医師から退院の許可が出た」と、妻から介護支援専門員(ケアマネージャー)に連絡があった。
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、「Fさんの退院後の在宅サービスを検討したいので病院に集まってほしい」と、在宅支援の関係者に会議への参加を依頼した。
訪問介護員(ホームヘルパー)は、ケアプランの検討のために病院に行って、会議に参加した。
会議には、主治医、病棟看護師、理学療法士も参加した。
トイレで転ぶのではないかというFさんの心配について話し合った結果、トイレに手すりが必要だということになった。
また、左足指に白癬(tinea)があり、薬が処方されていることも確認された。
手すりを設置する位置として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
解答:1
左半身の不全麻痺がある、Fさんに対しての手すりになるので、右側に手すりが必要。
立ち座りがしやすく、ボディメカニクスを考慮した手すりの位置はAになる。
試験ではボディメカニクスについて、上記のような問われ方もしますので、ボディメカニクスだけを理解していても解くのは容易ではないです。
事例の方のご状態を拾い、問題に取り組みましょう。
記事の最後に
出される問題が、複雑になってきましたよね。
介護福祉士の科目全体を大まかにでも把握する必要があります。
一通り、問題集を1冊終わらすことをおすすめします。
1回目の目的は解くことではなく
- 全体を把握すること
- 自分の得意、不得意な科目を見極めること
得意、不得意がわかったら
得意な科目からやっていきましょう。
なんなら不得意な科目はしばらく捨てるくらいの気持ちで大丈夫。
なぜか?それはまた、別記事でお話ししようと思います。
スポンサーサーチ
・大幅減量ダイエット
・【早い者勝ち!】 あなたのお名前、残ってる?


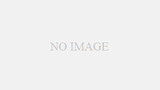

コメント