介護過程についてかんたんにご説明していきます。
介護過程の一番最初に行う、アセスメント。
アセスメントがしっかりできていると、その方らしさに寄り添うことができていきます。
アセスメントに時間を使うことはとても重要。
ですが、時間もあまり無い状況で、行うのも難しい。
だから、日々、その方を観察して記録して、常に考える。
私は、日々お手伝いさせていただいていることが、すでにアセスメントだと考えます。
モニタリングも同様。日々のかかわり、思考がとっても重要です。
この科目で、混乱しやすい「高齢者の生活自立度判定基準」について、このページだけで、自信をつけられるかと思います。
まずは、過去問題からやっていきましょう。
介護福祉士国家試験 第28回 問題63より
「関連する情報の分析・統合を通じて、利用者の課題、ニーズ、強みを明らかにすること」を表す用語として適切なものを1つ選びなさい。
1 チームアプローチ
2 アセスメント
3 モニタリング
4 アウトリーチ
5 インテーク
解答…2
これくらいだと、簡単ですかね?アセスメント、モニタリングくらいだと、聞き覚えがあると思います。
他の用語は聞いたことあるなーくらいの方がおおいのではないかと思います。
というか、私はそうでした。
では、介護過程について簡単にまとめていきましょう。
介護過程とは?

介護過程とは、介護の目的を実現するための過程の事。
客観的で科学的な思考と実践の過程。
では、問題選択肢の用語を簡単にご説明します。
アセスメントとは?(課題分析)
アセスメントとは、関連する情報の分析・統合を通じて、
利用者の課題や、ニーズ、強みを明らかにすること。
モニタリングとは?
モニタリングとは、 利用者の状況や支援の実施状況などを確認すること。
計画に沿った支援が実施されているかどうか評価をするため。
チームアプローチとは?
チームアプローチとは、複数の専門職がチームとなって連携して支援に当たる。
私の施設では、「多職種連携」という言葉のほうがなじみが深いです。
アウトリーチとは?
アウトリーチとは、援助者のほうから潜在的な利用者に出向き、相談や具体的な支援につなげる行動のこと。
利用者などが相談に来るのを待つだけではないということ。
インテークとは?
インテークとは、最初の面接の事。
介護福祉士国家試験 第28回 問題63 再挑戦①
「関連する情報の分析・統合を通じて、利用者の課題、ニーズ、強みを明らかにすること」を表す用語として適切なものを1つ選びなさい。
1 チームアプローチ
2 アセスメント
3 モニタリング
4 アウトリーチ
5 インテーク
正解以外の用語も理解した上で、問題が解けたかなあと思います。
介護福祉士国家試験 第27回 問題78
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準「ランクⅢ」の内容として、正しいものを1つ選びなさい。
1 日常生活に支障を来たすような症状、行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる
2 著しい精神状態や周辺症状、あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。
3 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。
4 日常生活に支障を来たすような症状・ 行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。
5 何らかの障害などを有するが、日常生活はほぼ自立しており、独力で外出する。
解答…4 日常生活に支障を来たすような症状・ 行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。
この問題については二種類の判定基準を覚えておく必要があります。
障害高齢者の日常生活自立度判定基準(寝たきり度)
自立「J」→準寝たきり「A」→寝たきり「B・C]の順で覚えましょう。
| ランク | 自立の範囲 |
| 生活自立「J」 | 何らかの障害あり 日常生活はほぼ自立 KW:外出 |
| 準寝たきり「A」 | 屋内:おおむね自立 外出:要介助 KW :準寝たきり |
| 寝たきり「B」 | 屋内でも要介助 ベッド上での生活が主体 座位は保てる KW:車椅子移乗 |
| 寝たきり「C」 | 一日中ベッドで過ごす 排泄、着替え、食事などは 要介助 KW:寝返り |
KW:キーワード
細かく見たい方は厚生労働省HPをご確認ください。
まとめると
ランクJ「ほぼ」
ランクA「おおむね」
ランクB「ベッド上が主体」
ランクC「1日中ベッド」
と結びつけ
「ほぼ」→「おおむね」→「ベッド上が主体」→「1日中ベッド」の順だと
覚えやすいのではないでしょうか?
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準は大きく5つに分かれる。
ランクⅠ~ⅣとランクM
細かく見たい方は厚生労働省HPをご確認ください。
ランクⅠ
何らかの認知症を有する。
日常生活は家庭内、社会的にほぼ自立。
KW:ほぼ自立
ランクⅡ
日常生活に支障を来たすような
症状、行動や意思疎通の
困難さが「多少」見られても
誰かが注意していれば自立できる。
KW: 困難さ多少
ランクⅢ
日常生活に支障を来たすような
症状・ 行動や意思疎通の
困難さが「ときどき」見られ
介護を必要とする。
KW:困難さときどき
ランクⅣ
日常生活に支障を来たすような
症状・ 行動や意思疎通の
困難さが「頻繁」に見られ
常に介護を必要とする。
KW:困難さ頻繁
ランクM
著しい精神症状(Mental symptoms)や
周辺症状あるいは
重篤な身体疾患が見られ
専門医療を必要とする。
KW:専門医療
まとめると
ランクⅠは 「自立」
ランクⅡ~Ⅳは「困難さ」
ランクⅡは 「多少」
ランクⅢは 「ときどき」
ランクⅣは 「頻繁」
ランクMは 「 Mental…」
と結びつけると
覚えやすいのではないでしょうか?
「困難さ」は
ランクの数字が大きくなるにつれ
「多少」→「ときどき」→「頻繁」の順に大きくなってく。
過去問のとおり
「障害」高齢者の日常生活自立度判定基準と
「認知症」高齢者の日常生活自立度判定基準を
混ぜて、選択肢に入れてくるので、混乱します。
「障害」高齢者の日常生活自立度判定基準は寝たきり度を判定するので、外出できるか?とか屋内での状態を表す。
「認知症」高齢者の日常生活自立度判定基準の場合、 「日常生活に支障を来たすような症状・ 行動や意思疎通の困難さ…」と表記されているものが多い。
問題の分解・整理
こうして、選択肢を見たときに、「障害」か「認知症」かで分けると、わかりやすくなります。
改めて、先ほどの過去問に挑戦しましょう。
介護福祉士国家試験 第27回 問題78 再挑戦①
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準「ランクⅢ」の内容として、正しいものを1つ選びなさい。
1 日常生活に支障を来たすような症状、行動や意思疎通の困難さが多少見られても。誰かが注意していれば自立できる
2 著しい精神状態や周辺症状、あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。
3 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。
4 日常生活に支障を来たすような症状・ 行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。
5 何らかの障害などを有するが、日常生活はほぼ自立しており、独力で外出する。
では、「障害」と「認知症」に分けていきましょう。
「認知症」
1 日常生活に支障を来たすような症状、行動や意思疎通の困難さが多少見られても。誰かが注意していれば自立できる
2 著しい精神状態や周辺症状、あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。
4 日常生活に支障を来たすような症状・ 行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。
「障害」
3 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。
5 何らかの障害などを有するが、日常生活はほぼ自立しており、独力で外出する。
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準「ランクⅢ」の内容として、正しいものを1つ選びなさい。
なので、「認知症」に分けたものから、ランクを付けていきましょう。
1 日常生活に支障を来たすような症状、行動や意思疎通の困難さが多少見られても。誰かが注意していれば自立できる
「ランクⅡ」
2 著しい精神状態や周辺症状、あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。
「ランクM」
4 日常生活に支障を来たすような症状・ 行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。
「ランクⅢ」
ランクⅢの4番が正解だとわかりますね。
ちなみに「障害」のほうにランクを付けると
3 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。
「ランクB」
5 何らかの障害などを有するが、日常生活はほぼ自立しており、独力で外出する。
「ランクJ」
しつこいようですが、最後にもう一度チャレンジしていきましょう。
介護福祉士国家試験再挑戦 第28回 問題63
「関連する情報の分析・統合を通じて、利用者の課題、ニーズ、強みを明らかにすること」を表す用語として適切なものを1つ選びなさい。
1 チームアプローチ
2 アセスメント
3 モニタリング
4 アウトリーチ
5 インテーク
介護福祉士国家試験 再挑戦② 第27回 問題78
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準「ランクⅢ」の内容として、正しいものを1つ選びなさい。
1 日常生活に支障を来たすような症状、行動や意思疎通の困難さが多少見られても。誰かが注意していれば自立できる
2 著しい精神状態や周辺症状、あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。
3 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。
4 日常生活に支障を来たすような症状・ 行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。
5 何らかの障害などを有するが、日常生活はほぼ自立しており、独力で外出する。
*解答は上に戻って確認してください!
[PR] 華珠も実際にお世話になっているきらケア 正社員紹介
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
本当にお疲れ様でした。
「役に立った!」「わかりやすかった!」
と思っていただけましたら、お気持ちを↓からいただけますとうれしいです!
ご支援金はブログ、youtubeの運営費にさせていただきます。
その他、社会福祉協議会や、ボランティア団体への寄付、災害支援金にもさせていただきますので、ぜひとも応援よろしくお願いいたします。
私が使っていたテキスト
実際に良く出る問題を抽出しています!読みやすく、学習が進めやすかったです!
法改正のポイントだけでなく、予想問題が本格的!実際、的中率も高いので本番前の力試しに
介護福祉士のための図鑑!鉄板でみんなもってます!合格した後もホントに役立ちます!
ケアマネにもなるんだ!介護福祉士のスキルアップのためにも、おすすめ!
関連動画・記事
その他、関連動画と記事をご紹介いたします。ご参考になさってください。
動画
「こころとからだのしくみ」直近3年の頻出ワード①
障害の理解 頻出
第32回 介護福祉士国家試験をやってみてわかったこと
個別アドバイス動画
youtubeのほうでも試験対策しています。介護職としてお話しなどもしていますので、よろしければチャンネル登録していただけますとうれしいです。
チャンネル登録はこちら↓

記事
2019年Amazonでよく売れたおススメの介護福祉士国家試験用テキストまとめ
資格取得リンク集
介護福祉士
介護職員初任者研修
ケアマネージャー
保育士などの資格取得リンクです。
全国のスクール情報満載。簡単比較、講座の無料一括資料請求。
シカトル講座情報や資格ガイド、一括資料 請求まで、個人のスキルアップ、キャリアアップの為のお役立ち情報満載!
その他資格取得リンク
【WOMORE】(ウーモア)女性のキャリアアップをサポートする資格・講座情報サイト
介護保険外サービス:訪問介護・訪問美容・介護相談・外出支援
千葉市で介護保険外サービスをお探しなら、地域密着のMAKE A LIFE.LLCへ





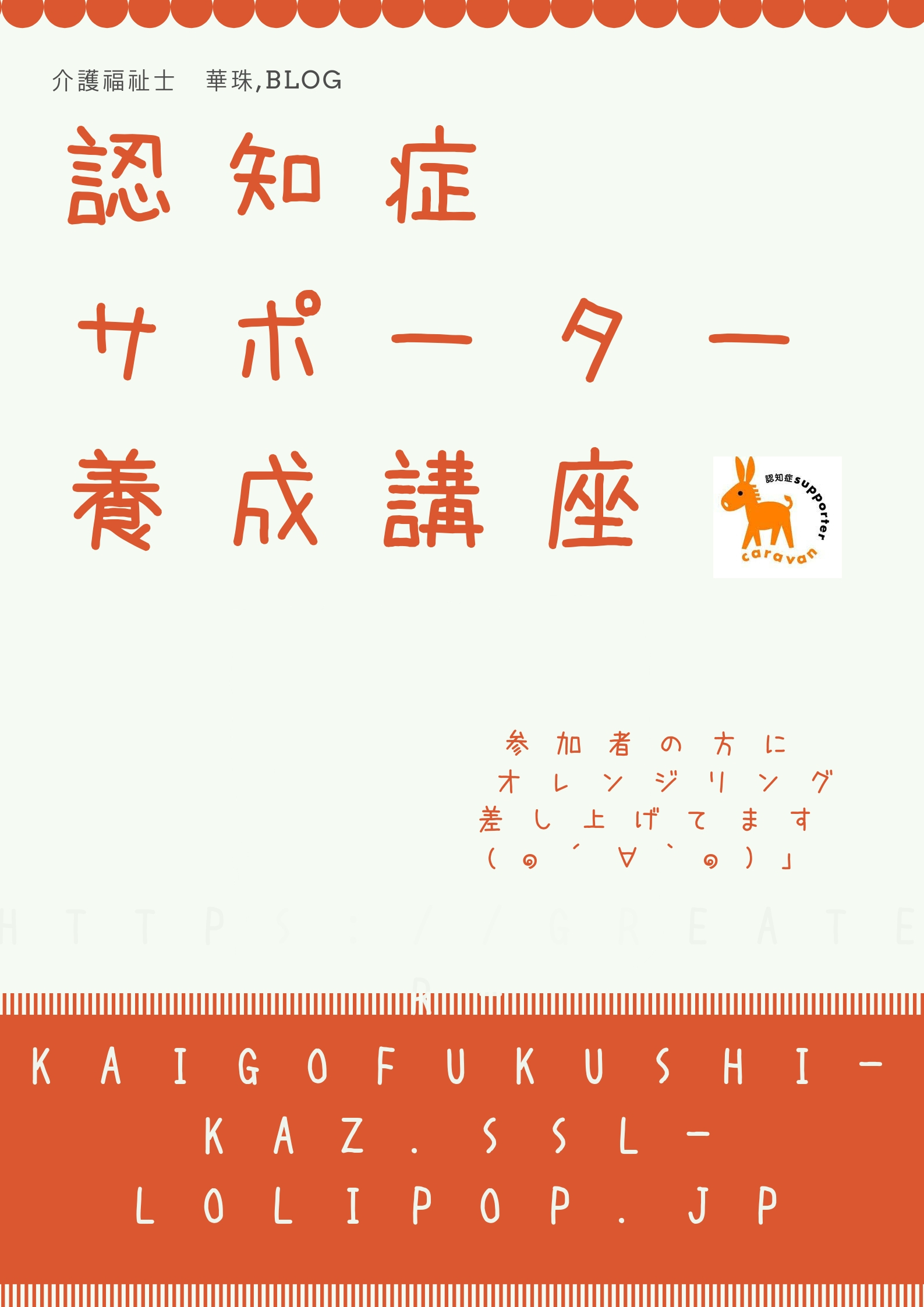
コメント
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] これだけで自信がつく!【介護過程】と【高齢者の生活自立度判定基準】関連過去問題利用者の生活の質の向上は介護過程の目的? […]
[…] これだけで自信がつく!【介護過程】と【高齢者の生活自立度判定基準】関連過去問題利用者の生活の質の向上は介護過程の目的? 「利用者の望んでいる,よりよい生活を実現する」介護過程の目的? […]
[…] これだけで自信がつく!【介護過程】と【高齢者の生活自立度判定基準】 […]
[…] これだけで自信がつく!【介護過程】と【高齢者の生活自立度判定基準】 […]
[…] これだけで自信がつく!【介護過程】と【高齢者の生活自立度判定基準】 […]
[…] これだけで自信がつく!【介護過程】と【高齢者の生活自立度判定基準】関連過去問題短期目標の設定に関する次の記述のうち,最も適切なものは? 介護計画の作成に関する次の記述のうち,最も適切なものは? […]
[…] これだけで自信がつく!【介護過程】と【高齢者の生活自立度判定基準】 […]
[…] これだけで自信がつく!【介護過程】と【高齢者の生活自立度判定基準】関連過去問題 […]
[…] これだけで自信がつく!【介護過程】と【高齢者の生活自立度判定基準】 […]
[…] これだけで自信がつく!【介護過程】と【高齢者の生活自立度判定基準】 […]
[…] これだけで自信がつく!【介護過程】と【高齢者の生活自立度判定基準】チェックテスト […]
[…] これだけで自信がつく!【介護過程】と【高齢者の生活自立度判定基準】チェックテスト […]
[…] これだけで自信がつく!【介護過程】と【高齢者の生活自立度判定基準】チェックテスト […]